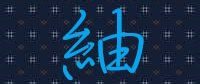「きもの文化検定」では、真綿(まわた)から紡いだ糸を使って織った紬(つむぎ)についての問題も数多く出題されます。
私は初めて、真綿と聞いた時、綿の一種かな?と思ってしまいました。
でも、『真綿』というのは、木綿(コットン)ではありません。
蚕のさなぎである繭から糸を引き出すのではなく、
繭を煮た後、全体を広げてわた状に引き伸ばしたものです。
軽くて、ふわふわで、あったかいんです。
真綿布団で寝たい・・・。
というわけで、紬は温かみがあり、着心地が良いのです。
今回は、「きもの文化検定公式教本I」の中の「織りの産地と特徴」の中から、
「紬」をピックアップいたしました。
やみくもに覚えるよりも、グループ別に分けて理解すると暗記しやすいです。
「きもの文化検定公式教本I」のその他の着物の主な産地と特徴はこちら
↓
《染めの主な産地と特徴》
《織りの産地と特徴:木綿》
《織りの産地と特徴:新潟県》
《織りの産地と特徴:沖縄県》
「きもの文化検定」の練習問題も解くことで、出題の傾向がわかりますので、是非、挑戦してみてくださいね。
目次
紬(つむぎ)とは
・絹織物の一種
・真綿糸や玉糸などを用いた先染、平織の織物
・全国各地で作られ、それぞれ特色がある
[きもの文化検定4・5級]
紬の説明で正しくないものを選びなさい。
(1) 紬は産地の名を付けたものが多い。
(2) 紬は真綿糸や玉糸などを用いる。
(3) 紬は格子、縞の柄が一般的である。
(4) 紬は二重組織になった紋織である。
解答 (4)
解説:紬は平織です。
[きもの文化検定4・5級]
真綿糸の作り方の説明で不適切なものを選べ。
(1) 蚕の繭は煮て柔らかくし、中のさなぎを取り除く。
(2) さなぎを取り除いた繭は、固く小さく丸めておく。
(3) 真綿から指先で糸を引出し、細長い糸状にする。
(4) 糸の太さは均一でなく、太い部分と細い部分がある。
解答 (2)
解説:繭を煮て柔らかく広げた真綿から、手で引き出して作る。
結城紬(ゆうきつむぎ):茨城県結城市
・重要無形文化財
・手つむぎ糸
・手括りで絣糸を作る
・地機で織る
・亀甲絣、蚊絣、縞、無地
[きもの文化検定4・5級]
国の重要無形文化財・結城紬の正しい説明は?
(1) 精練された絹糸で、ジャガード機で織る。
(2) 強く撚りを掛けた糸で織り、湯もみする。
(3) 真綿から手つむぎした糸を使い、地機で織る。
(4) 生糸を鉄媒染して染め、光沢のある生地に織る。
解答 (3)
解説 (1)は錦織、(2)は御召など、(4)は大島紬
牛首紬(うしくびつむぎ):石川県
・「釘抜き紬」:釘に引っ掛けても破れるどころか、釘を抜くほど丈夫と言われた
・玉繭(たままゆ:蚕2頭入りの繭)から糸を直接引き出す
[きもの文化検定4・5級]
「牛首紬」は何県で織られていますか?
(1) 山形県
(2) 滋賀県
(3) 石川県
(4) 青森県
解答 (3)
置賜紬(おいたまつむぎ):山形県
・米沢紬:植物染め(紅花、藍、刈安)
米沢周辺は紅花の産地→紅花紬
・長井紬:「米琉(米沢琉球)」
琉球産の織物に強い影響を受けた絣柄が発展
・白鷹御召:板締め技法、鬼シボ、小さな十字や亀甲柄の絣模様
[きもの文化検定3級・4・5級]
紅花染に使用されるベニバナの主な産地は?
(1) 山形県
(2) 岩手県
(3) 秋田県
(4) 福島県
解答 (1)
解説:山形県米沢周辺は紅花の産地
[きもの文化検定3級]
次の織物と産地(県)の組合せで誤っているものは?
(1) 置賜紬(山形県)
(2) 白鷹御召(富山県)
(3) 信州紬(長野県)
(4) 久米島紬(沖縄県)
解答 (2)
解説:白鷹御召は、山形県
信州紬(しんしゅうつむぎ):長野県
・上田紬:縞、格子柄
・山繭紬:天蚕糸で織る
・飯田紬:素朴な紬
・伊那紬:昔ながらの伝統
[きもの文化検定4・5級]
以下の中で一つだけ産地の県が違うものを選びなさい。
(1) 上田紬
(2) 伊那紬
(3) 久米島紬
(4) 飯田紬
解答 (3)
解説:久米島紬は沖縄県
大島紬(おおしまつむぎ):鹿児島県
・テーチキ(車輪梅)を染料とし、泥で鉄媒染する糸染め
・泥大島(泥染め)、藍大島(藍染め)、泥藍大島、色大島、白大島などがある
・昔は真綿から紡いだ紬糸で織られていたが、現在では生糸が用いられている
[きもの文化検定4・5級]
大島紬の説明について間違っているものは?
(1) 結城紬と並んで高級紬の代表
(2) 手紡ぎした紬糸で織り、後染めする。
(3) 地元に自生するテーチキで染め、泥で媒染する。
(4) 泥大島、藍大島、白大島がある。
解答 (2)
解説:昔は真綿から紡いだ紬糸で織られていたが、現在では生糸が用いられている。先染めである。
[きもの文化検定2級]
空欄に語群から適当な言葉を選び、文章を完成させなさい。
本場( ア )紬は奄美大島、鹿児島近郊などで織られている絹織物である。
また、本場( イ )紬は茨城県、栃木県などで織られている。
( ア )は( イ )に比べてさらりとした地風が特徴である。
また、( ア )の糸染めには( イ )では見ない( ウ )染めが伝統的である。
語群 (1)砂 (2)大島 (3)泥 (4)結城 (5)紅 (6)小千谷
解答 ア:(2) イ:(4) ウ:(3)
塩沢紬・小千谷紬・十日町絣:新潟県
→ 《新潟の織り》
久米島紬:沖縄県
→ 《沖縄の織り》
→ 久米島紬の画像
おまけ ☆ タイプ別の暗記法 ☆
「きもの文化検定」に必ず出題される、とわかってはいても・・・、
産地とか特徴とか、暗記するのは大変ですよね。
ご自分に合った暗記法で勉強すると効率が良いですよ。
自分のタイプが知りたい方は→タイプ別学習法
私は視覚優位型なので、イメージで暗記することが多いです。
例えば、、、
「牛首紬は石川県、別名:釘抜き紬」を覚えるなら、

石がたくさんある川を思い浮かべます。

その川を牛が渡っていきます。
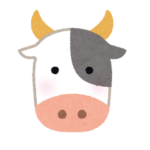
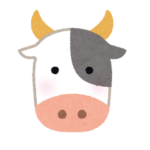
牛の首にクローズアップします。
「玉繭の2頭入り蚕」にかけて、2頭イメージ。
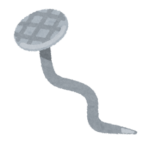
牛に引っ張られて抜けた釘とかイメージします。
こんな感じでストーリーにしても良いし、
カメラタイプの視覚優位型の方は1枚の写真の中に全て含まれるようにイメージしても良いです。
牛とかは簡単だけど、じゃあ、置賜紬とかはどうするの?
と言われますと・・・。う~ん。
「長いお米を白い鷹が召し上がったが、紅い花の所に山型に置いたままになってるなー」
(長井紬、米沢紬、白鷹御召、紅花、山形県置賜紬)
ちょっと苦しいですが、こじつけでも、何でもよいのです。
部分的にでもインプットしてしまえば、あとは広がっていきますから。
聴覚優位の方におすすめなのは、スマホのメモ機能とかに暗記したいことを録音して、運転中とか通勤中とか隙間時間に聞き流す事です。
私の経験上、その時、早口で録音しておくのが良いです。(速度が変えれるなら倍速で聞くとかでもOK)
速い方が脳が活性化されるし、リズムで覚えられるし、時間の節約になるからです。
いろいろ試して、自分に合った暗記法を見つけて、「きもの文化検定」合格に近づきましょうね!
・・・*・・・*・・・*・・・*・・・
あなたも、着物の世界を旅する仲間になりませんか?
↓
独学でも一人じゃない!一緒に頑張りましょう!!
私の日々の日常もお伝えしていますので、お勉強の苦手な方も、良かったら、お友達になって下さいね!お待ちしています!!